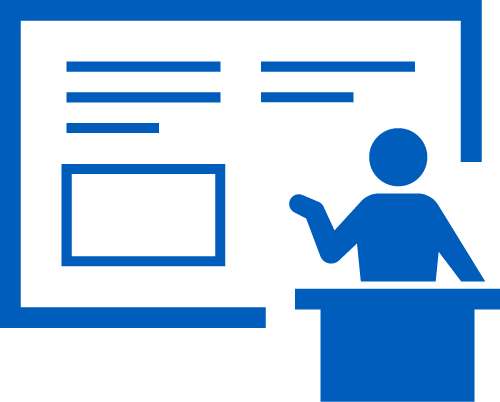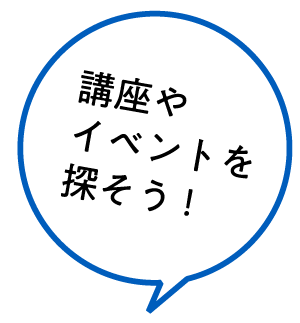
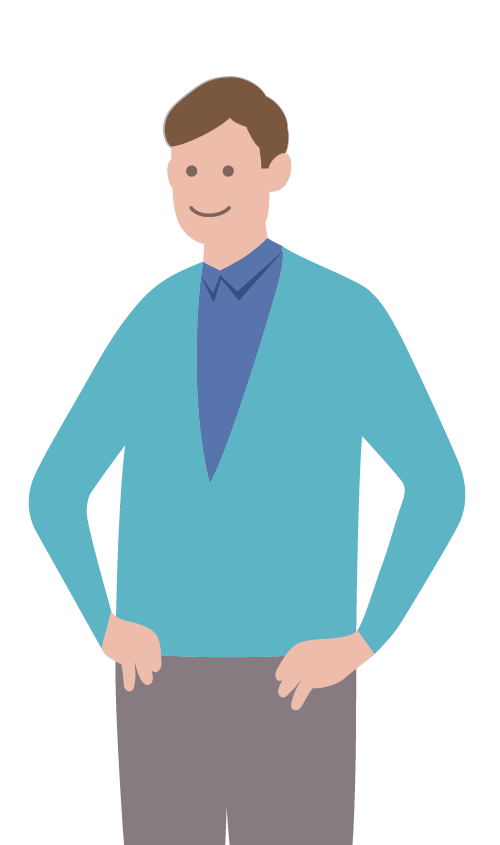 学ぶ
学ぶ
講座・イベント検索
- エリア:
- #中部(高知市を除く)
- カテゴリー:
- #文化・芸術 #語学・教養 #ICT(PC・スマホ活用) #音楽・ダンス・料理 #スポーツ #子育て #実験・科学 #野外教室 #イベント(レクリエーション・映画上映会・コンサート) #福祉・人権 #安心・防災 #健康・こころ・生き方 #学びなおし #ビジネス・スキルアップ #農・林・水産業 #地域づくり #その他
- 期間:
- 2026/02/26~2026/05/26
- キーワード:
- 指定なし